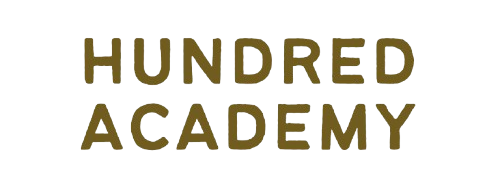僕は、「暮らしと自然」をテーマに2016年からいろんな創作活動に励んできました。
土、自然、アート、IT。
枠やしがらみに縛られないようにつくっています。自由であることを心がけています。







僕個人のテーマは、「暮らしと自然」。誰もが自分だけのテーマを決めて、自由に、自分の人生をつくることが出来ます。

僕はかつて日本中や東南アジアを放浪し、たくさんの「つくる人」を見てきました。どこに住んでいても、どんな経済状況でも、何かをつくっている人はみんな幸せそうでした。
世界にはいろんな不平等がありますが、「つくる喜び」は、僕たちに平等に与えられます。貧富の差や人種、信仰、ジェンダー、何も関係ありません。
日常の暮らしの中には、たくさんの創作の種が隠れています。僕たちは普通、「衣食住」はお金を払って手に入れるものだと思っています。水。エネルギー。食料。衣服。食器。家具。家。

でも、それが当たり前ではない世界もあります。僕が滞在したインドネシアの農村部では、衣食住から冠婚葬祭まで、いろんなもの自分たちでつくっています。
もちろん、とても大変な毎日です。でも、何でもDIYしてしまう彼らは毎日楽しそうで、僕のような旅人にも寛容で、家族や仲間を大切にしています。特に、子どもたちをとても大切にしています。
稲を育てる。鶏を飼う。家をつくる。村人全員で結婚式を催す。踊る。歌う。料理をする。毎日神様にお供えする。

僕が言っている「つくる人」は日本で言う職人のような特別な存在ではなく、普通の人です。
それは、日常の暮らしの中に、創造的な営みが内包されている人です。そんな存在に僕もなりたいと、この10年間を過ごしてきました。

科学やITや、最近ではAIがすごいスピードで発展し、暮らしに必要な衣食住がスマホのボタン一つで手に入る世界になりました。そんな環境に生まれた僕は、十分に幸せなはずです。
でも、僕はなんとなく物足りない気がしていました。正直に言うと、自分のことを幸せだとは全く思っていませんでした。

僕は自分の中に幸せの軸がなく、僕の幸せは周囲の人との比較で決められていました。心から喜んだり悲しんだりすることはありませんでした。「普通」というレールから外れないように、それだけを気をつけていました。
大人になるにつれて、歪みが大きくなりました。高校生の頃は学校に行けませんでした。せっかく入った医療の世界も、長続きはしませんでした。

20代の僕はどうやって生きていけばいいか分からずに途方に暮れていました。その当時は、自分で何かを生み出す力がありませんでした。僕は追い込まれた結果、創作的な世界に入っていきました。僕にとっての創作は、体も心も衣食住も人生も、すべてが対象です。

これは僕が手だけでつくっているマグカップです。ロクロも使わないし削りもしないので、表面がボコボコです。おそらく原始の時代と同じ陶器の制作方法です。
このようにボコボコのマグカップは、現代の画一化された商品の中では「傷物」かもしれません。効率化が求められる社会では、少ない労力でたくさん生産できる人が評価されます。ちゃんと作れない人や要領が悪い人は切り捨てられてしまう。

でも僕は、こういう形が整っていないマグカップが好きです。みんなが喜んでくれそうな柄を描いています。これは僕たちの暮らしに無くてはならないモノなのです。なんとなく心が豊かになったような気がしています。
僕は、大好きな自然の魅力を形にしたいと思って、POTOCOを作りました。僕たち夫婦がつくった小さな大自然はたくさんの人の手に届きました。これからも届けます。


僕がみんなに伝えたいのは、「つくる喜び」です。それは、効率化とか損得感情とはかけ離れた、自分だけの喜びです。つくることによって、僕は回復しました。
みんなに認められる必要はないし、お金にならなくても構わないと僕は思っています。その価値は自分だけが分かっていればよくて、その喜びを分かち合える人とたった一人でも出会うことが出来れば幸運です。