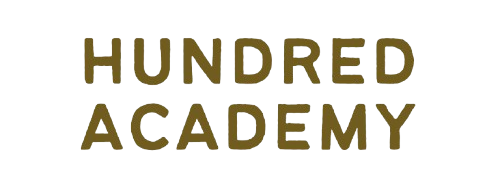食事は毎日数回、そして一生涯続けていく命の営みです。ですので、食事について学びを深めていくことはとても大切なことだと僕は思っています。
「食」に関して考えようと思ったとき、「どの食材が体に良いか、健康的か」といった食品の機能的な話題に目がいきやすいと思います。でも、まずは僕たち日本人の精神性や文化を改めて学ぶことがとても重要だと思います。
僕たち日本人が培ってきた食事の精神性や礼儀、マナーには人生全般に通じるあらゆる知恵が詰まっていると僕は考えています。他の命や自然へのリスペクトが根底にあって、僕たちの命や暮らしが成り立っています。そのような日本人が培ってきた精神を学ぶことが、結果的に自身の健康や幸福につながっていると僕は信じています。
日本人の食事の根幹にあるのは、「命への感謝」です。食事前後の挨拶、食事形式、素材の味をいかす出汁(だし)文化など、あらゆる場面にその精神性が隠れています。
①挨拶

「いただきます」「ごちそうさま」という食事前後の挨拶は、とても日本的な言葉で独特な文化です。僕たちは食事の度に両手を合わせながらこの言葉を言います。
レストランなどで、一人で食事をしている人が手を合わせていただきますと言っている場面を見かけることもあります。誰かと一緒にいるかどうか、人に見られているかどうかなどは関係がない行為なのです。僕はそのような人を見るとなんとなく嬉しくなるのです。ちなみに僕は外食の際は必ず店員さんにごちそうさまでしたと言葉で伝えます。
日本語のいただきます、ごちそうさまの根幹には「命に感謝する」という気持ちがあり、同時に「作ってくれた人への感謝」の意味も込められています。
僕は今までに数か所外国に滞在したことがあるのですが、やはり食事前後に手を合わせて命に感謝する所作をする人はなかなか見かけません。オーストラリアや東南アジアに滞在した際は、「さぁ、食べましょう」くらいの挨拶でした。
宗教における「神様に感謝します」という食事の挨拶は僕たちの「いただきます」の感覚に近いかもしれないですが、ちょっとニュアンスが違うような気もします。
外国の方と食事を共にすると、日本の礼儀が文化的に独特なものであると認識できます。単なる儀式的な挨拶ではなく、心の所作が形になったものであると僕は思います。
ちなみに先日、学校給食に関して「いただきます論争」が沸き起こりました。内容は「給食費を払っているのだから感謝を強要するな」というクレームが入った、ということでしたが、この情報が本当かデマか僕は知りません。具体的な情報がほとんど出てこないので、デマである可能性も十分にあるかと思います。
しかし、この情報、クレームに対して「そのとおりだ」と肯定した人はほとんどいないのではないでしょうか。日本人全体の感覚としてはほとんどの人が「違和感」を感じたように思われます。お金を払ったからいただきますを言わない、言うべきではない。このような感覚は僕たち日本人には理解できないと僕は思います。
②お皿を手に持つ

挨拶だけでなく、食事の形式や礼儀などの中にもこの「命に感謝する」という精神性が見受けられます。
たとえば、お椀を手に持って食べる行為は僕たちの精神性をよく表していると僕は考えています。日本に文化的な大きな影響を与えてくれた中国では、お皿をもって食べる行為は「がっついている」「犬食い」のように見えるためNGな行為です。アジア圏では一部お皿を持つ文化があるそうですが、基本はお皿は置いたまま食べます。
何よりも礼儀を重んじる日本人が何故、NG(諸外国のタブー)を犯してまで「お椀を持つ」食事スタイルを定着させたのでしょうか。

調べてみると、日本ではかつてお膳(個人ごとに用意される食事用の小さな卓)で食事をしていたため、お皿から口までの距離が遠くこぼれやすいので「お椀を持って食べる」ようになった、という情報が良く出てきます。
この理由もわかるのですが、僕はもっと別の理由がある気がします。例えば僕が滞在した東南アジアでは、お膳どころか床に直接お皿を置いて食べることもあったのです。ですが、お皿は持っていませんでした。農村部では床に平皿を広げて、手やスプーンで食べるのが一般的だったのです。
僕が考える日本人が皿を持つ理由としては、「食材を残さず食べる」という日本人の精神性が色濃く反映されているように思っているのです。
洋食のレストランで「平皿」「スプーン」「フォーク」などで食事をするとよく感じるのですが、お皿の中にある食材の切れ端やスープなどを完全にきれいに食べきることは至難の業です。食材の切れ端やスープ、ソースの一部が残ってしまいモヤモヤするのです。
しかし、手に持つことで食材との距離感が縮まり、箸と合わせることで米粒一つ残さずに食べることができます。お米、おかず、スープもほとんど全てお箸で完結させる日本人を見て、外国の人は驚くようです。
また、お皿に直接口をつけてすすることも日本独特ですが、これも汁の最後の一滴まで残さずに吸うことが出来ます。洋食のスープをスプーンで食べる場合、日本人レベルでキレイに食すのがとても難しく感じるかと思います。
お皿から汁をすする行為はアジア圏では一部で見られるようですが、欧米ではNGなようです。でも、これは「残さずに食べる」の究極系であるように思えるのです。

これには日本の文化的な側面である「大切なものを両手で扱う」という習慣も関係していると思っています。
日本人は大切なものを両手で扱う習慣があるように感じませんか。人から何か受け取るときは基本両手です。ドアや引き戸の開け閉めも両手を使うことが好ましいです。お茶の世界も両手で持って飲みます。片手で飲めるマグカップは近代になって初めて日本に根付きました。侍は日本刀を両手で持ちます。

両手で扱うという行為は、なんとなく「礼」の意味合いがあり、モノや行為そのものへのリスペクトがあるように思います。僕たち日本人は感覚的になんとなく分かりますが、日本人以外には全く分からないかもしれません。
このような精神的な背景も相まって、片手にお椀、片手にお箸と両手をフル活用する食事形式が生まれたのではないかと僕は考えているのです。
これによって食材を残さずにとてもきれいに食べることが出来ます。これらは諸外国では基本NGです。タブーよりも「命への感謝」を優先した僕たちの祖先は素敵だと思います。
③細い箸

「命への感謝」と「残さず食べる」を重要視した日本の文化として、「細い箸」にも僕は注目しています。
箸は元々5~6世紀ごろに中国や朝鮮から伝わったとされています。箸を使う文化圏は日本以外にもあるのですが、例えば中国の箸と日本の箸は少し違います。
中国の箸は長め(25センチ前後)で太くて先端には丸みがあります。一方、日本の箸は短め(18センチ前後)で、細くて先端がとがっているのが特徴です。
実際に太くて先端が丸い箸を使ってみるとよく分かるのですが、細かい動作には向いていません。平たい大きなお皿から食材全体をつかむときにはいいのですが、手に持った小皿から小さな食材をつかむのはとても難しいです。
一番それを感じる場面は魚を食べるときです。魚は小骨も多く、箸によってほぐしながら小骨を取り除かねばならない高度な技術が必要な行為です。
日本人が何故、箸を細く先端をとがらせていったのか。それは、お米の一粒から魚の一身まで残さずに食べるという精神性が強く表れているように僕は感じます。
特に、日本人はよく魚を食べる民族ですので、箸の形態が独自に進化したのではないでしょうか。魚だけでなく日本料理は細かくて繊細な料理が多いです。細くてとがっている箸は僕たちの文化であると僕は認識しているのです。
日本人は「手先が器用」とよく言われますが、このような民族性は「箸」から生まれたのではないかと思います。
このように、僕たちの食事様式の中には命や自然への感謝やリスペクトが内包されています。そのような視点で物事を見ると、いろんな気づきや学びがあるのです。例えば現代では「低カロリーが健康的」といった考え方が常識かと思いますが、本来の日本的感覚から見ると違和感を覚えます。カロリーとは生命が持つ熱量で、命の重みです。命の重みが大きいものほど、ありがたく食べるのが良いと僕は思っています。
無理なダイエットとリバウンドを繰り返しているような方がいましたら、ぜひそのような視点で食事を考えてみてください。食材を単なる機能や数字でとらえると、食事本来の幸せを見失ってしまうかもしれません。まずは食事の前後に手を合わせてみるのが良いかもしれません。