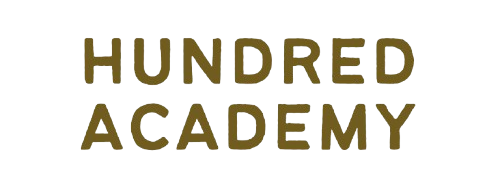僕の家庭には発酵文化が取り入れられています。ガーデンで採れた野菜を塩漬けにしたり、大豆で味噌を仕込んだり、なんとなく暮らしの中に溶け込んでいます。我が家では料理や発酵は妻が担当してくれています。
自分たちで仕込んだの漬物や味噌には、驚くほどの旨味を感じます。

特に僕たちの家庭では毎年たくさんの高菜を栽培し、塩漬けにしています。

高菜漬けは九州では日常的に食べられています。ご飯のお供はもちろん、ラーメンに入れたりチャーハンにしたり、パスタや焼きそばにも合います。

発酵食品は世界中でつくられており、文化として根付いたのはこの数千年ですが、おそらく石器時代からすでに存在したと考えられています。発酵食品が生まれたきっかけは、おそらく偶然。最初に出てきた発酵食はお酒やヨーグルトだろうと言われています。
発酵は、菌によって行われます。
発酵を担う微生物は大きく分けて『カビ(糸状菌)』『酵母』『細菌』。不思議なことに、発酵によって食品は腐りにくくなったり、味が深まったり、栄養価が高まったりします。
例えば、ブドウを潰して置いておくと皮についた酵母菌によって自然発酵します。これを飲んだ人が『美味しい』ことに気づき、ワインとなりました。しかも、腐らずに保存することが出来たのです。

かつての人々はそのような偶然の必見や経験を積み重ねていきまひた。何か目に見えないもの(菌)が、食べ物の味や香りを変えて保存もしてくれる。食料を計画的に生産していく中で『腐らせずに美味しくなる』菌を上手に見分け活用するようになったのです。
僕たちの身近でも似たようなことは起きます。

これは、我が家で仕込んでいる柿酢です。柿の表面にはもともと酢酸菌や酵母菌が付いていまして、瓶に入れておくだけで自然発酵するんです。
ちなみに、発酵と腐敗は紙一重のものです。人間にとって役に立つものを『発酵』、役に立たない、食べると危険なものを『腐敗』と呼んでいます。
どちらも『菌によって分解される』という原理は同じです。腐った食品は味・臭いが強烈で、食べたらおなかを壊す可能性もあります。また、発酵か腐敗かの判別は、地域や文化によっても変わります。

例えばこれは、シュールストレミングという食品です。世界で一番臭いと言われる食品として有名です。これは産卵前のニシンに塩をまぶして漬け込んだもので、嫌気性の乳酸発酵によって出来ます。そのまんま、腐った魚の臭いです。

僕たち日本人が大好きな納豆も、外国の人から見たら『腐った豆』かもしれません。食べることが出来ない外国の人も多いと聞きます。ネバネバ糸を引いている状況をみると、腐ってると思われても不思議ではないです。
その他、イヌイットのキビヤックや、中国のホンオフェなど、世界には発酵か腐敗か曖昧なユニークな食品がたくさん存在しています。

僕たち人類は日常で起こる発酵現象をよく観察し、その仕組みを解明してきました。顕微鏡がなかった時代から、目に見えない何か(菌たち)とコミュニケーションをとってきたのです。
そして人類は、発酵と深く関係があるのが「塩」である早い段階で気づきました。

食品を塩に漬けると、食品の中の水分が外に出されます。水分は濃度の低い方から高い方へ移動しますので、野菜の細胞から水分は抜けていくのです。
食品が腐る原因は、発酵に関わらない微生物が食品中の水分で繁殖するからです。食品が脱水されることで腐敗を起こす微生物は活動できなくなり、結果として腐敗が起きにくくなります。
腐敗菌の多くは塩分濃度5~10%で繁殖できないようになると言われているのですが、菌の中には『好塩菌』や『耐塩菌』と呼ばれる塩分濃度が高い状態でも活動できるものがいます。

発酵に関わる乳酸菌、麹菌、酵母などがこれにあたり、ある程度の塩分濃度でも活動するが出来ます。
腐敗を防げる塩分濃度『10~15%』は【腐敗は起きないけど発酵は起きる】絶妙なバランスです。この値の中で腐敗菌は死滅しますが、発酵菌は繁殖できるのです。

今日から発酵に触れてみたい、という人は、乳酸発酵漬けにチャレンジしてみてください。
乳酸発酵は、『乳酸菌』と呼ばれる菌を利用します。実は乳酸菌はどこにでも存在していて、私たちの腸内にもいますし、野菜にも自然に付着しています。
つくり方はシンプルで、2%の塩水に野菜を漬けるだけです。

我が家ではよく白菜やキュウリを乳酸発酵させます。
乳酸菌が野菜の糖分やタンパク質を分解し、甘味や旨みが増していきます。乳酸菌は副産物として『乳酸』をたくさん作るのですか、漬物の甘酸っぱい香りはこの乳酸によるものです。

野菜を着けたら常温で様子見し、うまく発酵していたら、ぷくぷくしたガスが出ます。
汁が白っぽくなって、甘酸っぱい匂いがしてきたら乳酸発酵が出来ています。