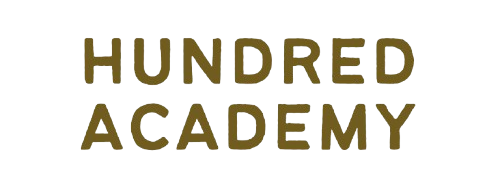健康やダイエットを考えるうえで最初に頭に浮かぶのはおそらく「食事」ではないでしょうか。健康やダイエットと食事を紐づけたビジネスは数えきれないほどの量があります。僕は現在34歳ですが、僕が覚えている範囲でも健康と食に関する様々なトレンドが生まれては消えてを繰り返してきたように思います。
健康、ダイエット、食に関する情報は膨大であり、これらを取り扱うのはとても難しいことであると思います。ある一つのテーマをとっても、専門家の中で肯定派と否定派に分かれます。例えば、近年では「低糖質」「ローカーボ」などがそうでした。
繊細な人はこれらの真偽がわからない情報によってものすごく心と体に影響を受けます。「これを食べたら太る・健康に悪い」といった恐怖心を食事の度に感じている人もいるのではないでしょうか。食事は1日数回、一生涯続けるものです。食事に関しての「構え」は人生全体の幸福に大きく影響するといっても過言ではないように思います。
ここからは僕の意見を述べますが、僕の意見をどのように解釈するかは個人にゆだねられます。どのようなテーマでも、専門家間で意見が分かれるということを忘れないでください。健康と食事をテーマにした絶対的な正解はないと僕は考えています。
①日本人の食事の変遷
食事と健康を考える場合、まずは僕たち日本人の食事がどのように変化してきたかを把握しておくことが重要です。「食べなければ太らない」「炭水化物は太る」というのは本当なのでしょうか。誰もが見ることができる一般的なデータの中に物事の本質が隠れています。
まずは日本人の1日の総摂取カロリーから見てみます。これらのデータは国民健康・栄養調査をもとにまとめたものです。
日本人の総カロリー摂取量の変化(1日あたり kcal)
1946年 約1,900 kcal 食糧不足で栄養失調が社会問題に
1950年 約2,050 kcal 配給制度が機能し始め回復傾向に
1955年 約2,260 kcal 経済復興・米の生産増加
1960年 約2,400 kcal 高度経済成長期の開始、米中心の食生活
1965年 約2,450 kcal 動物性たんぱく質の摂取が増え始める
1970年 約2,540 kcal 肉・乳製品の摂取増、食の欧米化の始まり
1975年 約2,470 kcal ピークに近い水準、米消費が減少し始める
1980年 約2,480 kcal ほぼピーク水準、脂質の割合上昇
1990年 約2,350 kcal 生活習慣病対策が始まり、食意識に変化
2000年 約2,200 kcal 外食産業の普及とダイエット志向の高まり
2010年 約1,950 kcal 高齢化・少食傾向、炭水化物摂取の減少
2020年 約1,900 kcal 戦後並みに低下(ただし栄養バランスは改善)
2023年(最新推定) 約1,870〜1,900 kcal 世界的にもかなり低い水準
日本人の炭水化物摂取量の変化(1日あたり g)
1945(終戦直後) 約420g 食料難で米中心の食事、量は減少しとったが主食比率高い
1950 約450g 米の消費回復、戦後の復興期
1960 約480g 高度経済成長期、米中心の食事継続
1970 約460g 米消費減少傾向、パン・麺が少し増加
1980 約430g 西洋食の影響で米の比率低下、炭水化物全体はやや減
1990 約410g パン・麺増加、米の消費さらに減
2000 約400g 食生活多様化、外食増加
2010 約380g 炭水化物摂取量減少、肥満増加との関連議論あり
日本人のタンパク質摂取量の変化(1日あたり g)
1945〜1950年頃 約50 g 戦後で食料不足、動物性タンパク質は少なめ
1960年代 約55 g 経済成長で肉・卵・乳製品の摂取増加
1970年代 約60 g 肉や魚中心の食生活が一般化、摂取量増加
1980年代 約65 g 高タンパク食が定着、洋食の影響も大きい
1990年代 約70 g 外食・加工食品の普及で摂取量増加傾向
2000年代 約70 g 男性・女性ともに安定、健康志向で過剰摂取は少なめ
2010年代 約70 g 摂取量はほぼ横ばい、魚よりも肉中心傾向
2020年頃 約70 g 高齢化で摂取量は横ばい、サプリやプロテイン利用増加
日本人の脂質摂取量の変化(1日あたり g)
1945〜1950年頃 約30〜35 g 戦後すぐで食料不足、油脂はほとんど不足気味
1960年代 約40 g 経済成長で油脂の摂取増、揚げ物やマーガリンが普及し始める
1970年代 約50 g バター・サラダ油・肉の摂取増加
1980年代 約60 g 高脂肪化が進む、洋食の影響も大きい
1990年代 約65 g 脂質の割合がカロリーの25〜30%前後に到達
2000年代 約60〜65 g 健康意識の高まりで少し抑制傾向
2010年代 約55〜60 g 油脂摂取は横ばいかやや減少、魚油や植物油中心に
2020年頃 約55 g 食生活の多様化で全体的には安定、飽和脂肪酸摂取は減少傾向
日本人の成人肥満率の変化(男性 女性 %)
1945〜1950年頃 約3〜5 % 約5 % 戦後すぐは食糧不足で肥満はほとんどいなかった
1960年代 約5〜7 % 約6〜8 % 食生活の変化でわずかに増加
1970年代 約10 % 約10 % 高カロリー・高脂肪の食事が普及し始める
1980年代 約15 % 約12 % 肉・揚げ物の摂取増で肥満が増加
1990年代 約20 % 約14 % 外食やファストフードの影響も大きい
2000年代 約25 % 約20 % 男性の肥満率が女性より高くなる傾向
2010年代 約30 % 約21 % 健康意識で女性の増加はやや抑制、男性は横ばい
2020年頃 約33 % 約22 % 男性は安定、女性は少し増加傾向
これらをまとめると、現代の日本人は終戦直後よりもカロリーを摂取していない、つまり食べていないことがわかります。そして、炭水化物を食べる量も大きく減っています。しかし、不思議なことに日本人全体の肥満率は増えています。
「食べたら太る」「炭水化物を食べたら太る」という僕たちが持っているイメージとは合いません。食べなくなっているのに肥満が増えている。この流れはとても重要で、不思議に思うべき点だと思います。
一方、カロリー摂取量や炭水化物摂取量が減っているのに対して、たんぱく質や脂質の摂取量は増えています。
②量よりも質
データを見ると、単純に「食べる量」によって肥満率が決まるわけではないことがうかがえます。ちなみに、肥満率と生活習慣病の罹患率は密接に関係しています。肥満と同様に生活習慣病も増えています。
「食べる量が減っているのに肥満が増える」という現象に対して「運動量が減ったから」と考える人もいます。たしかにオフィスワークが増えた現代では体を動かす機会は減りました。でも、僕はそれはあくまで1つの要因に過ぎないと思います。
僕が重要だと思うポイントは食事の「質」です。僕たちは食事によって熱量(エネルギー)を摂取していますが、その内訳は炭水化物、たんぱく質、脂質の三つがあるのです。
傾向から考察しますと炭水化物を食べる量は減って、たんぱく質や脂質は増えています。僕はここに食事と健康を考えるうえで最も大切な鍵が隠れていると思っています。
③健康な食事
日本人のデータを見たうえで自分にとっての健康な食事を考えることが大切です。万人にとって正解はないと思うので、それぞれが自分に最適な食事を考えていきましょう。
僕の普段の食事をご紹介します。僕は摂取カロリーの大半をお米から摂っています。
お米/みそ汁(具だくさん)/発酵食品(漬物)/納豆/魚(たまに肉)
僕の食事や体の特徴としては
〇お米からカロリーの大部分を摂る
〇おかず(主菜)が少ない
〇発酵食品が多い
ということです。ちなみに僕は加工食品はあまり食べません。出来るだけ素材から調理をします。また、サラダ(生野菜)もあまり食べません。食事ではないですが、清涼飲料水(ジュース)を飲むことはほとんどないです。この食事を普段のルーチンにしていると体の
調子が良く過剰に太ることもありません。
僕が重要だと思う食事のポイントをまとめてみます。
〇生まれた国や地域でずっと食べられている食材を選ぶ
「ブルーゾーン」という統計的に健康で長寿な地域を調べた研究があります。ブルーゾーンは世界中に点在していますが、食べている食材は多種多様です。彼らに共通しているのはその地域で昔から採れる食材を食べている点です。
ざっくりですが、僕たちアジア圏では、「お米、魚、発酵食」の組み合わせが多く、ヨーロッパ圏では「小麦、肉(乳製品)、酒」の組み合わせが多いです。その地域に根差した食材は遺伝子レベルでそこに住む人々の体に合う可能性が高いと思われます。僕たちは腸の長さも存在する腸内細菌も違います。食材そのものに善悪のジャッジをするのではなく、自分に合うかどうかが重要だと考えます。
〇出来るだけ加工されていない食材を選ぶ
例えばお米には、玄米と白米があります。白米の方が加工されています。白米は玄米の状態から胚芽や外皮を取り除いたものですが、これはつまり食物繊維を取り除いたということです。統計的なデータとして、食物繊維を取り除いたもの(加工品)よりも素材そのままの食材の方が健康には良いと言われていて、僕も間違いないと思います。
つまり「みかん」をそのまま食べることと、それを絞った「みかんジュース」を飲むことは違います。100パーセント果汁であっても、食物繊維を取り除いた(加工された)時点で体への影響は違います。お米や小麦でいえば食物繊維が残った「全粒粉」のものの方が血糖値の急激な上昇はなく太りにくくなります。
〇シュガーには注意する
現代人はシュガー(糖)を過剰に摂っている可能性が高いです。炭水化物は「糖質」と「食物繊維」からできています。炭水化物の糖質は「多糖類」という大きな物質ですが、分解されて小さな単位になっていきます。砂糖は「二糖類」、ブドウ糖は「単糖類(一番小さい単位)」です。
シュガー(二糖類)、単糖類を過剰に摂取するのは注意が必要かと思います。僕たちの暮らしでいうと清涼飲料には多量に含まれています。炭水化物も言わば「糖質」なのですが、二糖類や単糖類とは体への吸収のされ方が違います。小さな糖類ほど体には急激に吸収され、血糖値が急上昇します。炭水化物は多糖類であり、食物繊維とセットになったもので吸収が緩やかなのです。
〇おかず(脂質)を少なくする
日本人の脂質摂取量は年々増えてきましたが、肥満率が上昇していく原因として大きいと僕は考えています。脂質を過剰に摂取してしまう要因は「おかずの量が多い」こと。脂質の大半は普段のおかずに含まれています。
「おかずを減らそう」という意識を持つと普段の食事が苦しくなります。ダイエットが苦しいのと同じ理由です。我慢が伴うのです。そうではなくて、「他の食材を増やす」ことに意識を向けるのが良いと思います。僕の食事では具沢山のみそ汁と発酵食品が必ず食卓に並びます。おかずがなくともそれさえあればご飯一杯は美味しく食べることが出来ます。ご飯のお供として優秀なのが発酵食です。うま味や噛み応え(漬物は食物繊維がそのまま残っている)によって食事の満足感がものすごく高まります。おかずは少量で済むのです。
〇体温を保つ
しっかり食べると体温が上がります。例えば女性の基礎代謝は1100kcalくらいですが、体温が1℃上昇すると代謝は10~13%くらい上がります。つまり体温が高いと生きているだけで消費するカロリーが高くなるのです。
基礎代謝が10%上がったと仮定すると、一日に消費するカロリーは110kcal多くなり、一年だと40150Kcal多くなるのです。これはおよそ5.6Kg分の脂質に相当します。体温を一度上げるだけで一年後、5.6Kgの脂質を減らせるのです。なので、重要なのは食べないことよりも食べること。しっかり食べて健全に体型を維持する、これが大切だと思います。