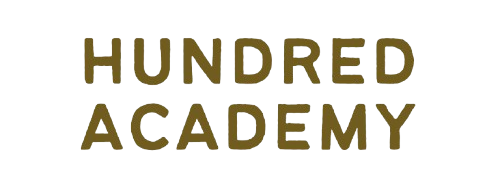「1」の自分から「100」の自分になろう。
自分の技術や生き方を一つの枠に縛らず、出来ることを少しずつ増やし、自分の可能性を100に広げていく。
「ハンドレッド」は、僕たちの可能性を広げるための標語です。
僕は元々医療という一つの枠の中で生きてきましたが、今では作物を育てたり、布や陶器をつくったり、家をつくったり、料理や発酵食をつくったり。好奇心に従ってなんでもします。

つまり僕は「まとまらない人」です。いい加減落ち着いてちゃんとしなさい、と咎められたこともありますが、でも僕は、まとまらない人をやめるつもりはありません。
パーマカルチャーの創設者であるビル・モリソン氏が、このような人物でした。彼は急速に破壊されていく自然を保全するために、永続的な暮らしのデザイン手法としてパーマカルチャーを生み出した人です。
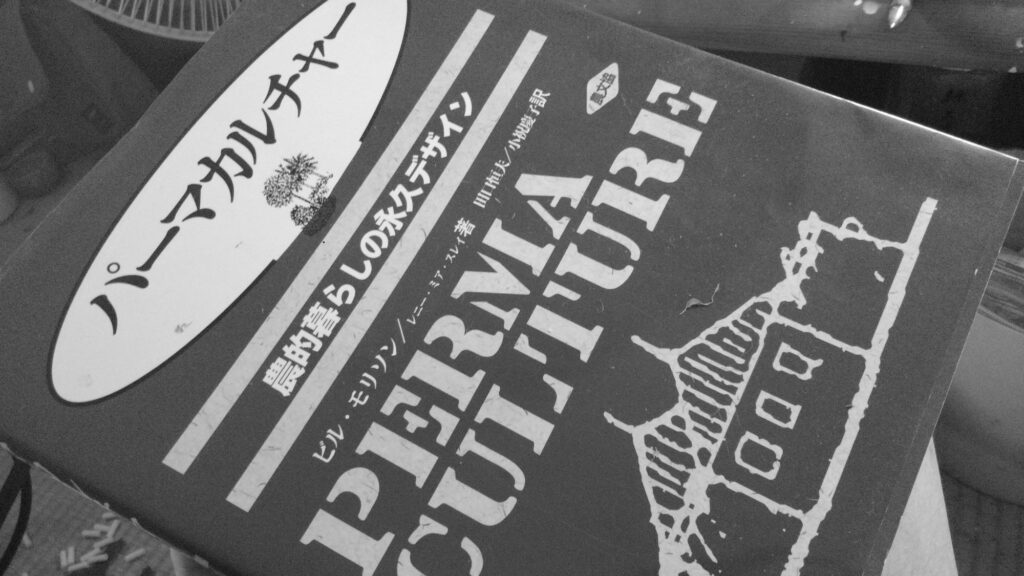
私はタスマニアの小さな村で育った。必要な物は何でも自分たちでつくった。靴も自分でつくったし、金属の細工もした。魚も捕ったし作物もつくったし、パンも焼いた。仕事を一つしか持っていないという人は見たことがなかったし、およそ仕事と呼ぶべきものを持っている人はいなかった。誰もがいくつものことをして暮らしていた。28歳ころまでは、まるで夢のような暮らしをしていた。
自分たちの暮らし、衣食住に必要なものを、何でも自分たちでつくる。彼はこのような創造的な暮らしを「夢のような暮らし」と表現しています。誰にとっても「つくる」ことは大きな喜びが伴うのです。
外国では特定の呼び名がなかったこのような存在。それは、なんでもやっちゃう、まとまらない人。
そんな人たちのことを、僕たちの日本では「お百姓(ひゃくしょう)様」と呼んできました。

僕が放浪したインドネシアの深い農村部は、今でもこのようなライフスタイルを送っています。それぞれの職業や役割に分かれつつも、みんなで稲や野菜を育てたり、季節によって漁をしたり布を作ったり、冠婚葬祭を催したり。
とても大変な生活ですが、彼らは毎日楽しそうでした。家族や仲間、特に子どもたちを大切にしています。

彼らは個人が幅広くなんでもこなすことで、お互いに支え合うことが出来ています。これは、「人」や「職」の壁を曖昧にして、ゆるく混ざり合いながら暮らしをつくっていくアジア的なライフスタイルかもしれません。
このような、まとまらない生き方は分業化や専門化が進んでいる現代の日本とは視点が違います。

なぜなら現代では「特定の職に就く」ことが当たり前で、「自分に出来ないことはすべてお金を払って解決する」ことが疑いようがないほど常識だからです。だから僕たちはいい学校、いい会社に入って、たくさん稼げる人になることを望まれます。
このようなライフスタイルは仕事の効率が上がり経済が発展するというメリットがある一方で、「お金がなければ生きられない」というデメリットもあります。
今、スマホのボタンを一つ押せば、衣食住に必要なものはほとんど手に入ります。人や自然との関係がなくても、生きていけるのです。
でも、そんな「安全・便利・快適」なシステムに依存してしまう暮らしには、リスクが隠れているように思います。
病気になる。怪我をする。仕事がなくなる。災害でライフラインが止まる。お金がなくなる。
そうしたときに、人や自然との関係がゼロだと、生きるための糧がなくなってしまいます。ここに僕たちの漠然とした不安があるのだと思うのです。
僕たちは気づかないうちに攻撃的になったり、排他的になったり、損得感情の波に押し流されたり。うっかりしているとそんなふうになります。

そんな時代だからこそ、僕には力が湧いてきます。なぜなら僕は、自分や家族や仲間のために解決したいと思う課題がたくさんあるからです。世間が言うように、貯金やら投資やらで資産を貯めれば、自分たちの世代まではなんとかなるかもしれません。だけど、僕たちが死んだあとも、子どもたちはこの社会で生きていくのです。
課題は挑戦のチャンスでもあります。
何をやってもうまくいかない孤独な20代の僕は、自宅の小さな庭や近所の空き地に野菜の種を蒔くことから始めました。小さな一歩でしたが都市部でも自給自給できると分かり、夢中で取り組みました。

そんな道の途中では妻とも出会いまして、彼女は僕の取り組みを事業にして、会社にまで成長させてくれました。僕一人ではただの「まとまらない人」でしたが、仲間のおかげで「ハンドレッド」という理念を掲げる企業として、社会の中で生きられるようになったのです。
こんな僕でもちゃんと生きているので、みんなも大丈夫だと思います。