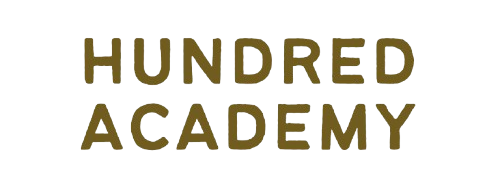生きていくために、お金が必要。
これは疑いがないくらい常識なことで、僕もそう思っています。僕が持っているお金は、僕の体と時間を使って生み出した「価値」です。それが形になったものなので、お金は「命そのもの」と言っても過言ではありません。僕は自営業をしているので、特にその価値を痛感しています。
僕は生きるために一生懸命働いて、外貨を得ています。僕は働いて得たお金で、自分に必要なものを借りたり、買ったりします。
水。ガス。家。スマートフォン。時計。コーヒー豆。靴。車。

僕は、自分ではつくれないモノを他の人から買っています。例えば僕はcheapCASIOの腕時計が大好きで、毎日つけています。ここまでオシャレで精密で頑丈でしかも安価な時計は、今の僕では逆立ちしてもつくることは出来ません。僕はリスペクトを込めて、お金を払ってCASIOを買っているのです。
僕が払ったお金は、僕に価値を提供してくれた人の元に行きます。受けとった人は、そのお金で自らの暮らしを営むことができます。そんなふうに、いろんな人の手を渡りながら循環しています。
お金は、僕たちが役割を分担して助け合うためのチケットです。なぜなら、確かな価値を担保したものがなければ、僕たちは安心して価値を交換することが出来ないからです。

でも、お金というのはあやふやな存在でもあります。僕たちが使っている「円」は高くなったり低くなったり。近年、日本ではモノの値段が上がり続けています。生活するのにかかるコストや税金が重なり、苦しい状況に追い込まれつつあります。

なぜ、日本で売られているモノの値段があがるのでしょうか。それは、僕たち日本人が、生きるために必要なエネルギーや食糧を外国から買っているからです。
石油。天然ガス。小麦。大豆。鉄鉱石、など。僕たちは、自分たちではつくれないいろんなものを外国からもらっています。当たり前の話ですが、外国の人はそれらを無料でくれるなんてことはありません。僕たちは外国から資源や食糧をもらう代わりに、僕たちからも何か価値のあるものをお返しする必要があります。この世界は一方向のみの贈与ではなく、交換で成り立っているからです。

僕たち日本人はモノづくりが得意なので、かつては自動車や家電などを外国に売っていました。だけど現在は、外国の人に買ってもらえません。その理由はシンプルで、外国の人が僕たちがつくるモノを欲しがらないからです。それは、「僕たち日本人は外国の人が欲しがる魅力的なモノをつくれなくなった」ということを意味します。
僕たちは外国からモノを買いたい。でも、外国の人は、日本からモノを買いたいと思わない。

物々交換を思い浮かべてみます。自分は、価値のある誰もが欲しがるものを持っている。だけど相手は、価値の少ないガラクタばかりを持っています。価値のあるもの一つと、ガラクタ一つでは交換したくありません。価値がつりあうように、もっとたくさん渡すように要求すると思います。
近所のパン屋さんが高くなっているのは、アメリカから小麦を買うために必要な「日本の価値」が低くなったからだと僕は考えています。最近は気候変動や戦争などの影響を受けて小麦の価値自体が上がっていますが、本質はそこではないと思っているのです。
問題の根本は、僕たち日本人が価値のあるモノを生み出せなくなってしまったことです。投資で資産を増やせば乗り切れるというのは個人の話で、日本社会の全体を俯瞰した場合はあまり意味がないと僕は思っているのです。
そうは言っても、僕たち個人がどのようにこの困難を乗り越えていけばいいのか。僕は、自らが創造的な暮らしを送ることでその糸口を探してきました。正しいかどうかは分からないですが、僕には個人的な考えがあります。
まず僕が大切だと思うのは、「自分の物差し」を持つこと。価値判断の自分軸、と言ってもいいかもしれません。今みんなが「高い」と言っているものは、本当に、間違いなく、高いのでしょうか。よく分からないことを理解するためには、自分の経験に落とし込むことが一番の近道だと思うのです。

例えば僕たちは、野菜を自分で育てています。僕たちは野菜を育てる手間と苦労をよく知っています。日本では野菜の価格は乱高下し、全体的には少しずつ上がっていますが、それが何故かを僕たちは想像することができます。
肥料はどこからくるのか。気候変動で野菜にどんな影響があるのか。人手不足な状況がどれほど大変なのか。
お米や野菜が「高い」と感じている人は多いと思います。でも、僕たちの感覚では「高い」とは感じません。僕は自分の実体験に基づく感性から語っています。安売りを買うのは嫌ですし、適正な価格を払いたいと思ってます。僕が特別裕福だからではありませんし、お米や野菜が高くなると家計が苦しくなるのは同じなのですが、「高く」はないのです。それは、実体験に基づいた生産者へのリスペクトがあるからです。

僕たちはコットンを栽培して布をつくることができます。そんな僕たちにとって衣服、特にファストファッションは安すぎると感じます。なぜこんなに安いのか、その理由も想像できます。そこには割を食っている人や自然が存在すると思っています。
頭だけで考えてイメージした世界と、実体験に落とし込んだリアルな世界は違います。日本中の人が高いといっても、僕たちの物差しではそうではありません。
「円が安い・弱い」というのは、あくまでも日本と外国を比較したときの話です。だから僕は自分軸をつくって、自分の物差しで価値を測ることが大切だと思っているのです。自分で生み出すことが出来れば、軸がぶれません。モノの価値というのはいろんなレイヤーから眺めることが出来ることを伝えたいです。

もう一つは、「お金を介さない世界」を持つこと。
例えば、僕が滞在したインドネシアの農村部では、お金を介した人間関係があまりありません。イメージでいうと、何かを考えたり取り組んだりするときの主語が、「わたし」ではなく「わたしたち」なのです。彼らの暮らしでは、食料生産も、子育ても、冠婚葬祭も、みんなで取り組みます。「生きる」ことを営むうえで、お金のやりとりは少ないのです。人と人、人と自然の関係性そのものに価値がある。彼らとともに生活をすると、それを実感できます。
そうは言っても、完全な自給自足の世界ではありません。若くて体力がある若者はスマホを活用していますし、町に出て外貨を稼ぎます。スマホの活用の巧さは、僕たちよりも上かもしれません。実際僕は10年前(2015年くらい)にuberを使いこなす若者たちを見て驚いたのです。
もちろん、村から少し行けばお店もあります。そこではちゃんとお金を使うのですが、みんな顔見知りなので「高く売ってやろう」なとと思う人などいません。僕たち旅人に対しては高く売ろうとすることもありますが、僕がその人の友達の友達だとわかると、普通の価格で売ってくれます。そんな世界なのです。身内を大切にしています。

僕自身も、お金を介さない世界を持っています。野菜を育てているのもその一つです。家族がいる福岡から離れないのもその一つです。家をつくるのもそうです。

自分でつくろうと思ったら、実際には自分ひとりではできないことが多いので、人と協力することが必然になります。人や自然との関係性を見直すと、生活コストはとても低くなるのです。だから、たとえお米の値段があがっても僕たちは動じません。助けてほしいときに、助けてほしいと素直に言うこともできます。

こんなふうに、現代を生き抜く自分なりの方法を探していくことが、僕なりの一歩一歩です。日本という大きなものを考えるのなら、僕たちが「価値」を生み出せる人間になることがマストだと思います。
そして僕は、子どもたちが幸せだと感じる社会をつくることでしか、未来は切り開けないと思っています。