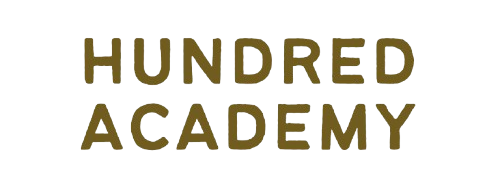健康であることは、僕たちが幸せに暮らすうえでとても大切な要素です。僕は医療職として生きてきたので、健康や病気に対して考えることはとても多かったのです。家族を病気で亡くす経験もしました。
僕は、病気や障がいを治すことよりも、健康を増やすサポートをする方向に進みたいと思っています。医療という枠組みではなく、人生、ライフスタイル全体を見て健康というものを捉えたいと考えています。
僕は健康についてたくさん調べ、自分の実体験も積み重ねた結果として、僕が個人的に大切だと思うものは
「食」「ライフスタイル」「生きがい」の三つです。
ブルーゾーン研究というものがありますが、僕はこれがとても参考になると思っています。僕のこれまでの実体験ともピッタリと合っています。
これは、統計的に健康で長寿な地域を見つけて、そこに住む人々がどんな生活を送っているのか調べるといったものです。日本では沖縄がブルーゾーン入っています。その他の地域としては、「イタリアのサルディーニャ島」「アメリカ合衆国カルフォルニア州ロマ・リンダ」「コスタリカ・ニコヤ半島」「ギリシャ・イカリア島」があります。

健康を構成するのは、心と体です。僕たちは体(あるいは食)の部分には注目するのですが、本質的には「心」の部分が重要ではないかと思うのです。なぜなら、ブルーゾーンの人々の最大の特徴は、「豊かな人間関係」や「生きがい」を持っていることだからです。
健康について確かな正解はないと思います。自分で考え、実体験によって納得できる健康を探すことが大切だと思います。
①食

まず初めに押さえたほうがよいのは、その食材自体で「健康」「不健康」の明確に判別をするのはとても難しいことです。米、小麦、肉、乳製品、どのような食品でも批判の対象になることがあります。でも、僕は食材そのものを善悪で判断することはしないようにしていますし、仮に思うことがあっても言わないようにしています。偉い学者さんの間でも意見が分かれますし、あやふやな情報を発信するのは無責任だと思うからです。
統計的に見ると、長寿で健康な地域では、昔からその土地や文化に根ざした食材が食べられている傾向があります。世界の食文化を大まかに分類すると、アジアは「米、発酵食、魚」、ヨーロッパでは「小麦、肉(乳製品)、酒」が代表的な組み合わせでよく食べられています。住んでいる環境によって手に入る食材が変わり、その状況に人も適合していくのです。

例えば沖縄では医食同源の考え方が根本にあり、米、豆腐、野菜、豚肉、魚介などをバラエティ豊かに組み合わせていますし、ギリシャのイカリア島では小麦、野菜、ハーブ、蜂蜜などが豊富です。イタリアのサルディーニャ島は小麦、チーズ(羊)、豚、野菜、魚介などが食べられています。共通するのは土地や文化に根差していること、そして食材の加工が比較的少ないということです。
こう見ると僕たちが普段食べている食事と大差はないように思います。「炭水化物は太る・不健康」という認識を持っている人がいるかもしれないですが、小麦が主食で健康な地域も普通にあるのです。食材自体の是非というよりも、その食材が自分に合うかどうかが大切だと思います。

僕個人の食生活は、玄米(たまに白米)、みそ汁(自家製野菜と味噌)、漬物(自家製)、納豆をベースに、おかずは魚(たまに肉)がメインです。カロリーの大部分を米と大豆からとっています。質素に感じるかもしれないですが、家庭菜園や自家製発酵食が多い我が家の家庭料理に僕は大満足しています。一汁一菜を基本とした食事にすると、食事の準備も楽で精神的にとても良い状態になります。






僕の場合、その日の食事の内容によって元気に動ける度合いがかなり変わることを実感しています。毎日の食事ルーチンが崩れると、空腹感や倦怠感が気になるようになります。
僕の体感としては、食物繊維がとても重要な要素だと考えています。食事の大部分を占める玄米、みそ、漬物すべてに食物繊維が豊富に含まれています。食物繊維は腸内細菌にとって重要なのはよく知られています。さらに、繊維質というのは胃腸でゲル状になるのでゆっくりと消化吸収が進みます。炭水化物は分解されて「糖質」になるなのですが、砂糖のように一気に吸収される糖質とは全く違うのです。ゆっくりと消化吸収が進むことが大切です。
つまり、食材の「食べ方(食材の加工の度合い)」も重要な要素でして、玄米と白米では体への影響は違います。加熱した野菜と漬物でも違います。僕にとっては食材に繊維質を残しておくことが大切なのです。できるだけ加工が少ない食材の方が、僕の健康にとっては良い傾向があるということです。
僕は、体感を通して自分に合った食事を探していくことが大切だと思います。テレビやインターネットで見かけるような「バランスの良い理想的な食事」のイメージで食事をしますと、僕の場合は太りやすくなりますし体調も悪くなります。主に米からエネルギーをとる僕のライフスタイルでは、現代の食事はおかずの量が過剰であると感じるのです。
実際日本人が摂取する総カロリーは昭和に比べるとかなり減少していますし、実は僕たちは終戦直後よりも摂取カロリーが低いのです。また、お米(炭水化物)の摂取量も減少しているのですが、不思議なことに肥満者や生活習慣病の数はとても増えています。低カロリーやローカーボという食事は本当にヘルシーなのか、今一度考えてみてもいいかもしれません。
②ライフスタイル
健康長寿の地域では日常的に無意識に近い領域で軽い運動をしています。

どういうことかというと、例えば「和室」。
居室が畳の部屋の場合、一日の中で何度も床からの立ち座りが必要になります。洋室のテーブル+椅子文化と比較すると日常で行う運動量にかなりの差が出てきます。たとえば1日に5回だけ床からの立ち座りを行うとしても、1年で1825回、10年で18250回になるのです。僕の自宅もほとんどが畳の部屋なので、一日に何度も床からの立ち座りを行っています。無意識に運動しているような毎日です。

その他にも、庭仕事などがあります。家庭菜園やガーデニングでも立ち座りやしゃがみ込みを頻回に行います。また、家庭菜園では季節に合わせて計画を立てながら種まきや収穫をするので、頭の体操にもなるのです。
住んでいる地域の「地形」なども大きな影響があります。

例えば、イタリアのサルディーニャ島が良い例です。坂道が多い込み入った地域の人は健康・長寿になりやすいです。つまりは山間部などの地域です。標高は関係なく、重要なのは道の勾配です。坂道を歩くのはかなりの負荷がかかります。山間部の人は日常的に坂道を歩くことで健康につなげています。現地の様子を映像などで見ますと、そのような地域は山間部の込み入った場所で、車も走れないような環境が多く歩くしかないのです。
このように見ていきますと、長寿の地域では「無意識の軽い運動」が日常の中にたくさん含まれていることがわかります。しかもこれらはジムで行うような運動とは違い、周囲の環境を把握しながら動くために、五感をフルに使いながら行う運動なのです。
もちろん、「無意識の軽い運動」ができる環境がない人は、意識的に運動を行うのがベターです。ブルーゾーンであるカルフォルニアのロマリンダでは、ジムやプールでの運動が盛んなのです。
③生きがい

「生きがい」という日本の言葉は、外国でもikigaiと呼ばれています。日本人特有の感覚で、なかなか翻訳出来ないのかもしれません。外国の人にとっては「信仰」という言葉が近いようです。
健康長寿の方々の最大の特徴は、「豊かな人間関係」や「やりがいのある仕事」この二つが暮らしの中に存在していることです。
例えば沖縄では人の集まりが多いです。
模合(もあい)という文化が残っていて、これは「友人などが定期的に集まって、毎月一定額を出し合って積み立てていく。そのお金で困っている仲間を助ける。(特に何もなければ積み立てたお金を順番に総取りしていく。)」という相互扶助の文化だそうです。僕が沖縄に滞在した際は若者の間でもご高齢の方の間でもその文化が残っていました。特に用事もないのに人が自然と集まってきて、歌ったり踊ったりする光景に僕はカルチャーショックを受けたのです。
また、イタリアのサルディーニャ島の地域では毎日人が集まります。お年寄りを一人で過ごさせるということがありません。友達や身内で集まって、みんなで過ごすのです。誰もがそのコミュニティ内で役割を持ち、大切な存在であり続けるという文化があります。また、その地域ではお年寄りは大きな「知恵」を持つ存在としてリスペクトされています。

ちなみに、世代で分けずに老若男女みんなで集まるということはとても重要です。これはそのお年寄りの方にとってのみ大切なのではありません。子どもにとって重要なのです。
その人が健康長寿になる要因として、「小さい頃にお年寄りと過ごしたかどうか」が重要であるという研究もあります。
小さい頃に元気な祖父母に面倒を見てもらった子どもは、そのたくましいイメージを生涯持ち続けたまま自身も年齢を重ねていくのです。そのように大人になった人は自身が高齢になるまで、そして高齢になっても元気で意欲的である可能性がかなり高まります。だから、いろんな年代がミックスされた集まりをつくるというのは健康においてかなりの影響があるということです。

そしてなにより重要なのが、やりがいのある仕事。それは、「自分がだれかの役に立っているという実感」を与えてくれます。自分の存在意義というあやふやなものが、健康にとて極めて重要な要素です。僕も心から同意しています。

生きる気力というのは誰かとつながり、その人の役に立ちたいと思ったときに湧いてきます。これは、「朝、目覚める理由がある」とも言い換えることが出来ます。自分は、何のために毎朝目覚めるのか。生きているのか。この理由の中に「誰かの役に立ちたい」という動機が入ると、人間は強くなります。
自分の仕事に誇りを持つこと。家庭菜園、裁縫、料理、どのような日常的な仕事も立派な健康要因になります。

こうやっていろんな角度から健康を考えていきますと、健全な心や体をつくっているのは意外なものが多いように感じます。「伝統的な食事」「和室」「坂道」「繋がり」「生きがい」など、一見するとあまり重要ではなさそうな要因が多いですが、僕は的を得ていると思っています。特にお金がかかることではないですし、意識を持てばだれでも実現できそうなことばかりです。