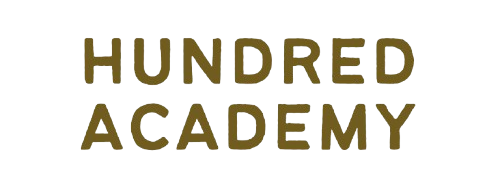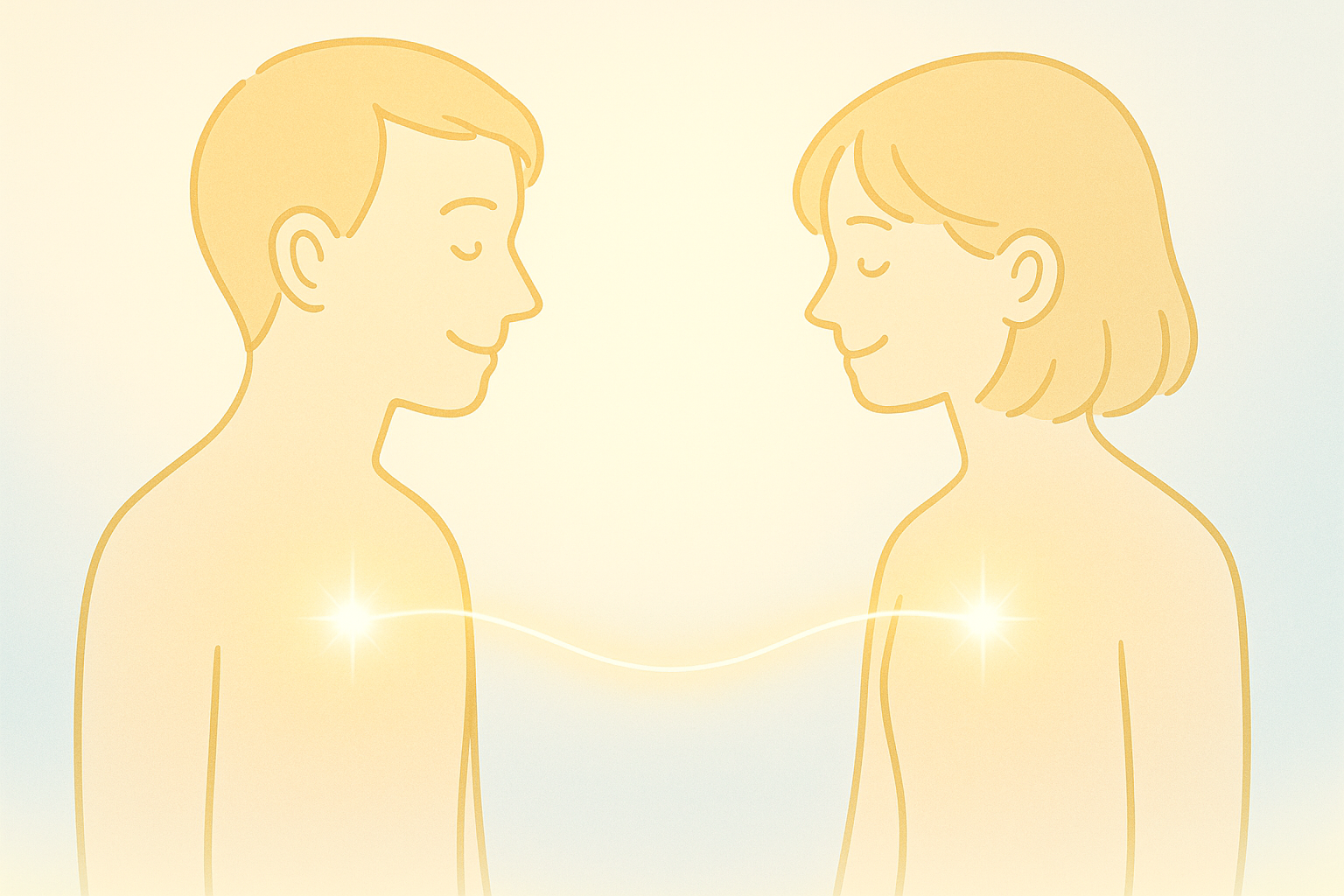共感する脳のふしぎ
他人の不機嫌に自分の感情が引っ張られる。誰かの笑顔を見て、自分まで明るくなる。そんな経験はありませんか?
僕たちの脳には、他人の行動や感情を“自分の中に映す”神経ネットワークがあります。それが「ミラーニューロン」。

誰かの笑顔を見ると、自分の脳の中でも笑顔の神経が動き出す。誰かが悲しんでいるのを見れば、自分の中でも同じ痛みが再生される。それは大脳で考える理性的な思考ではなく、進化の過程で身につけた、ほとんど自動的な神経反応なのです。
けれど今の社会は、その本能を働かせる余白を失いつつあります。スマホの画面の向こうで人の感情を見続け、比べ続けるうちに、脳は疲れ、共感の回路が鈍くなっていく。人と関わることが「しんどい」と感じるのは、心が冷たくなったのではなく、共感の神経が過剰に痛みを受け取っているから。
この文章は、そんなあなたに読んでほしい。人の痛みに敏感すぎる人、他人と比べて苦しむ人、あるいは人の気持ちがわからないと悩む人。あなたの中の“感じる脳”を取り戻すために、ここから、ミラーニューロンという小さな奇跡の物語をたどっていきます。
人はなぜ共感できるのか

1990年代、イタリアでのサルの研究から、他者の行動を見ただけで自分の運動神経が反応する「ミラーニューロン」が発見されました。これは、他者の動きを脳内で模倣するという驚くべき現象でした。
これはどういうことかというと、
あるサルがピーナッツをつかもうとしたときに反応する運動ニューロンが、ほかのサルや人がその動作をしているのを“見ただけ”でも同じように反応したのです。
つまり、自分は動いていないのに、脳の中では“まるで自分がその動作をしているかのように”神経が動いていた。これが「ミラーニューロン(鏡の神経)」と呼ばれる仕組みです。
この発見は、「見ること」と「感じること」が想像以上に深くつながっていることを示しました。私たちは誰かの行動を見た瞬間、無意識のうちにその人の動きを“脳の中で再生”している。だからこそ、人の表情やしぐさを見ただけで感情が伝わったり、共感したりできるのです。
その後、2000年代に入ると、人間の脳のfMRI研究で、他人の痛みや悲しみを見たときに島皮質や前帯状皮質が活動することが分かりました。この活動パターンが、「他人の痛みを見ると、自分の痛みを処理する神経が反応する」──いわば“ミラーニューロン的”な現象として注目されました。
このように、他者の感情や経験を自分の中で再現する仕組みは「ミラー機構(mirror mechanism)」と呼ばれるようになりました。心理学や社会神経科学の分野では、この広い概念をまとめて“ミラーニューロン”と呼ぶこともあります。

このミラーの仕組みは、人間だけの特別なものではありません。鳥は仲間の歌声を聞くと、自分が歌うときと同じ神経が働き、犬は飼い主の表情で感情が変わる。イルカや象は仲間の悲しみに寄り添う行動を見せる。共感は文化ではなく、生命が生き延びるために選んだ戦略なのです。
他者の行動を見ただけで学ぶという能力は、群れの知恵を共有し、生存を高めました。孤立して戦うより、共に感じ、支え合うほうが強い。ミラー機構こそが、社会を生み出した神経の土台なのです。
感情はうつる──比較の苦しみもその延長にある

誰かの笑顔を見ると、僕たちの脳神経はその笑顔を模倣シミュレーションしてしまう。だから、思わず自分も笑ってしまう。誰かの悲しみに触れると、自分の胸まで痛くなる。この“仕草や感情の伝染”は、ミラー機構が働いている証です。
けれどその仕組みは、ときに苦しみも生み出します。たとえば、ミラー的反応が敏感な人は、他人のイライラや不安に自分も引っ張られてしまう。
逆にミラー的反応が鈍感な人は、他人の気持ちに反応できず、人間関係を築くのが苦手になってしまう。
他人の暮らしや生活が可視化されるようになった現代社会では、次のような問題も生じます。
たとえば、他人の幸福を見たとき。脳の中では幸福な人と同じ「快」の神経が反応します。しかし、自分が現実世界で同じ報酬を得ていないと感じた瞬間、扁桃体(脳にある、恐怖の誘発装置みたいなもの)が不快を知らせ、前帯状皮質がその“差”を検出する。それがあの、胸のざわめきや焦り、劣等感の正体です。
つまり、他人の感情を映し出すミラー機構と、報酬系がその“差”を計算する──この組み合わせが、人と比べてしまう脳の構造です。
SNS社会は、この脳の構造を巧みに刺激します。他人の喜びを見る → 自分の中でも喜びが再生される → しかし現実の報酬がない → 不快になる → さらに他人を見る。このループは、ミラー機構とドーパミンが繰り返し反応する神経の渦です。それを繰り返すうちに、脳は疲れ果て、共感が痛みに変わる可能性があります。
感じる脳は変わっていく──環境と可塑性の視点から
僕たちの「感じる力」は、生まれつきの性格ではなく、これまで生きてきた環境によって形づくられています。他人の感情に過剰に反応して疲れてしまう人もいれば、逆に人の気持ちがわからず悩む人もいます。でも、どちらも間違いではありません。それは、脳がその人なりの方法で“自分を守ろうとしてきた結果”なのです。

たとえば、子ども時代に怒りや緊張が多い家庭で育つと、脳は「感情をそのまま受け取るのは危険だ」と学習します。
その結果、人によっては心を閉ざして鈍感になり、感情を遮断して自分を守ることもある。
逆に、他人の怒りや不機嫌をいち早く察知し、敏感に反応してその人から距離を取ることで自分を守ることもあります。
鈍感さも、敏感さも、どちらも「危険から身を守るための脳の知恵」。どちらかが悪いわけではなく、それぞれが生き延びるための戦略なのです。
マインドフルネスとは“観察する脳”を育てること
マインドフルネスとは、この“観察する脳”を育てる実践です。

他人の感情に巻き込まれそうになった瞬間、「今、僕の脳に他人の怒りが入ってきている」と気づくだけで、前頭前野(理性)が働き、扁桃体(恐怖のセンサー)の興奮を落ち着かせてくれます。
一方で、鈍感な人も同じように、まずはそのままの自分を受け入れることから始まります。「感じにくい」ことは欠点ではなく、心が自分を守ってきた証です。無理に何かを感じようとする必要はなく、ただ「今、自分は何も感じていないな」と気づくだけでいい。その小さな気づきが積み重なるうちに、少しずつ身体や心の感覚が戻っていきます。
その気づきを繰り返すうちに、前頭前野とミラー機構のネットワークが強化され、「感じること」と「考えること」が少しずつ統合されていきます。マインドフルネスの実践は、前頭前野の調整力を高め、共感ネットワーク全体のバランスを整える可能性があります。
感じすぎる人も、感じにくい人も、そのバランスは意識の向け方によって変えていける。脳は、これまでの経験を越えて、いつでも新しい反応のしかたを学び直すことができるのです。どんな感じ方も、かつての自分が生き延びるために身につけた方法。でも、これからは「感じながらも飲み込まれない」方向へ、少しずつ進んでいけます。
ミラー機構は、僕たちを苦しめることもあれば、救うこともあります。それは、他人の痛みを感じる能力であり、同時に、思いやりの源でもあるからです。喜びを分かち合う力でもおります。
感じる力を否定せず、ただ気づいて観察する。その積み重ねの先に、人と人との関係が少しずつやわらかく変わっていきます。共感の痛みも、孤独の鈍さも、すべては“感じる脳”が生き延びようとする証。そしてその脳は、今この瞬間も、静かに変わり続けているのです。