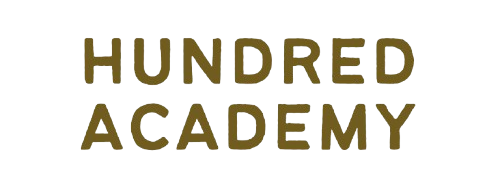日本の味の根っこは、すべて麹菌から
僕たちが「日本の味」と聞いて思い浮かべるもの。
味噌、醤油、みりん、そして酒。
どれも少しずつ違う香りを持ちながら、どこかで同じ温もりを感じます。
それは偶然ではありません。
すべての根っこに「麹菌(こうじきん)」がいるのです。
麹菌は、目に見えない小さな命です。
けれど、その存在がなければ、僕たちの食卓は今とはまったく違うものになっていたでしょう。
米を甘く、豆を香ばしく、穀物を旨みに変える。
発酵という現象の裏で、静かにすべてを支えています。
ただ、ここで一つ不思議なことがあります。
麹菌は「カビ」の一種なのに、自然界には存在しません。
森や空気中に漂うような野生の菌ではなく、僕たち人間が育ててきた菌なのです。
しかも、毒を出しません。
それどころか、安全で、おいしさを生み出す力を持っています。
世界を見渡しても、そんなカビはほとんど存在しません。
“人と共に進化した菌”。
それが麹菌です。
日本人は、長い時間をかけてこのカビを見極めてきました。
危険な菌を避け、食材を腐らせず、香りのよいものだけを残す。
そうやって少しずつ、“人間にとって心地よいカビ”が選ばれていったのです。
つまり、麹菌は自然が生んだ偶然ではなく、
人間と自然のあいだで選び抜かれてきた命なのです。
麹菌は、ただの発酵の主役ではありません。
それは、日本という環境と感性が生み出したひとつの生命文化です。
僕たちの味噌汁の香り、
醤油の深い旨み、
酒のやわらかな甘さ。
そのすべてに、
日本人が1500年かけて“選び取ったカビ”の物語が生きています。
自然界に存在しない“人と菌の共同体”
麹菌という存在は、自然界のどこにもいません。
森にも、土にも、野生の穀物にも。
僕たちが出会う麹菌は、すべて人間の暮らしの中で育ってきたものです。
つまり麹菌は、人間が“つくりだした”命であると言えます。
もとは毒を持つカビ。
放っておけば、食べ物を腐らせ、時には僕たちの命を奪う。。
けれど日本人は、その中に潜む「変化の力」に気づいたのです。
食べ物を壊すのではなく、
“別の何かに変える”力。
僕たちの先祖は安全な株だけを選び取り、何世代にもわたって受け継ぎました。
苦い、えぐい、腐敗臭のある菌は捨て、
甘く、香りのよい菌だけを残しました。
そして何百年もその菌を使い続けるうちに、
麹菌は人の暮らしに合わせて変化していったのです。
麹菌は、もう自然界に戻しても生きられません。
人の手のぬくもりと、穀物の温度の中でしか育たないのです。
麹菌は、自然の子でありながら、人間の家族になりました。
世界中を見ても、そんな関係を築いた民族はほとんどいません。
この菌は、単なる発酵の道具ではなく、
「人と自然が共同で進化した証」なのです。
1500年かけて人が選び取った命
麹の歴史は、古墳時代にまで遡るとされています。
『古事記』や『播磨国風土記』には、
すでに麹を使った酒造りの記録が残っています。
つまり、日本人は1500年以上も前から、
この小さなカビと共に暮らしてきたのです。
その長い年月の中で、
麹菌はまるで人間の家畜のように育てられてきました。
ただし、動物のように飼われるのではなく、
「共に生かされる」存在として。
家ごとに、蔵ごとに、菌の系統が受け継がれました。
気候、風、木の匂い、米の種類。
その土地の条件に合わせて、
菌たちは少しずつ姿を変えていきました。
危険な菌は淘汰され、
安全で穏やかな菌だけが残る。
その繰り返しが、何世代にもわたって積み重なってきたのです。
こうして人間が“選び続けた”結果として、
現在の麹菌は、毒を出さず、
食材を旨みに変える“世界唯一の安全なカビ”が生まれました。
人間の手と感覚が、
時間の中で自然と交わりながら“進化を導いた”結果なのです。
世界が忌避した“カビ”を日本だけが受け入れた理由
世界の多くの文化では、カビは“不浄”としてあまり受け入れられてきませんでした。
西洋では、カビは“腐敗”の象徴。
キリスト教の文化圏では、「清潔」と「不浄」が明確に区別され、
腐敗やカビは“不浄”として避けられてきました。
清潔さは神聖のしるし、腐敗は堕落のしるし。
だから、カビを食に使うという発想は、長く受け入れられなかったのです。
一方で、日本は違っていました。
日本では、自然そのものが神でした。
山にも、川にも、風にも、命が宿る。
カビもまた、その一つの姿として見られていました。
腐ることも、変わることも、命が循環している証。
日本人にとって、自然の中で起きる変化は、
破壊ではなく再生の一部でした。
だからこそ、
日本では「カビを殺す」よりも「カビと共に生きる」という発想が生まれました。
その延長線上に、麹菌があります。
カビを敬い、
カビを観察し、
そして、安全なカビだけを残していきました。
宗教ではなく、暮らしの哲学として。
日本人は、“腐敗の中に生命のリズムを見た”民族なのです。
八百万の神と、菌を敬う感性
僕たち日本人は、自然を「管理するもの」とは考えませんでした。
自然は、コントロールする対象ではなく、対話する相手でした。
山には山の神がいて、
川には川の神がいて、
風にも稲にも、命が宿ると信じられてきました。
“八百万の神”という言葉は、単なる多神教ではありません。
それは「この世界に存在するすべてが、同じ生命の循環にある」という思想のかたちです。
この感覚が、麹菌を受け入れる基盤になりました。
西洋では、カビは「汚れ」でした。
けれど日本では、「変化の兆し」でした。
何かが腐るとき、それはただ命が死ぬのではなく、
別の命に姿を変える途中だと感じられていたのです。
麹菌は、まさにその象徴でした。
米を分解しながら、甘みに変える。
大豆を発酵させながら、旨みに変える。
一見“壊している”ように見えて、実際は“生かしている”。
腐敗と発酵の境界線は、ほんの一枚の紙のように薄い。
でも、日本人はその微細な境界を感覚で感じ取ってきました。
麹菌は、目に見えない自然の声です。
それを封じ込めず、耳を傾けたのが日本人でした。
この感覚は、宗教でも哲学でもなく、暮らしの知性です。
自然を敵にせず、命のリズムの中で調和して生きる。
その積み重ねが、「発酵」という文化を生み出しました。
そしてこの文化は、言葉にも深く刻まれています。
“発酵”。
「発(ひらく)」+「酵(生命のはたらき)」というこの言葉は、
命がひらいていく瞬間をそのまま表しています。
つまり、日本人にとって発酵とは、
命の扉が開くことだったのです。
カビを忌み嫌うのではなく、
そこに生命の続きを見出す。
それが、日本人が「麹菌」という存在を育てることができた理由だと思います。
麹菌は、日本という思想のかたち
麹菌は、単なる発酵の菌ではありません。
それは、「日本」という思想が生み出した命のかたちです。
世界には、文明を築くために自然を切り離した国が多くあります。
自然は支配の対象であり、人はその上に立つ存在でした。
けれど、日本は違っていました。
自然を外側のものとは見なさず、
自分の内側の一部として受け入れてきたのです。
たとえば、季節の移ろいに敏感な文化。
桜が咲くとき、散るとき、
そこに「生と死のつながり」を見る。
それは、日本人が無意識に持つ感性です。
麹菌もまた、その感性の延長線上にあります。
カビは腐敗の象徴でも、生命の再生の象徴でもあります。
人は、菌をコントロールして食を得るのではなく、
菌の働きに自分の手を合わせるようにして、一緒に生きてきたのです。
人が自然を選ぶのではなく、
自然が人を選び、人が応え、共に変わっていく。
麹菌は、まさにその“共進化”の記録なのです。
そして、この関係性は日本文化全体にも通じています。
自然と人間のあいだに“線”を引かない。
発酵とは、その呼吸のかたちです。
腐敗と再生の境界線で、命がもう一度ひらく。
麹菌は、その瞬間の象徴です。
そしてその菌を育て続けてきた日本人の感性こそが、
“発酵する文明”を築いたのです。
制御ではなく、共存。
合理ではなく、調和。
排除ではなく、循環。
日本という文化は、
自然と人のあいだで発酵を続けています。
僕たちが味噌汁をすする音、
醤油の香り、
酒のぬくもり。
そのすべてが、
人と自然が1500年かけて育てた対話の証です。
麹菌は、
日本という思想が選び取った命。
そして、
僕たちがいまも受け継いでいる小さな神様なのです。